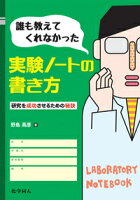553回
「継続は力なり」になっているかどうか定かではありませんが,2009年4月に北里大学で働き始めてから10年間,担当したすべての回の化学講義をこのブログで記録・公開してきました.
2009年4月の第1回から数えて昨年12月まで,数えてみたら553回でした.
ブログには講義をおこなった後の記録だけでなく,大学に関連したさまざまなものごとを記録しています.
最初の記事は2009年2月22日(日)です.東京大学生産技術研究所から北里大学一般教育部に移ることが決まって,仕事内容も環境も大きく変わるので,せっかくだから日々の記録を残そうと考えたのでした.
最初の記事はコレです↓
www.tnojima.net
今は「Life + Chemistry」となっているこのブログの開設時のタイトルは「大学1年生の化学」というものでした*1.担当するのは1年生だけで,主に化学の講義録を残して行こうと考えたからです.
もったいないので
研究に関する日々の仕事の記録は,学術論文,講演要旨,特許明細といった形で公開されて行きます.
しかし,講義とか演習とか学生実験とかについては,一般的には,記録を残して公開して行くわけではありません.
それなりの労力を費やして準備しているにもかかわらず,担当時間が終わったらそれっきり,といいうのはもったいないものです.
もったいないので,ブログにして公開して行こうと考えたのでした.
最初の講義は2009年4月15日(水)1限,医療工学科
北里大学に来て最初に化学講義をおこなったのは,2009年4月15日(水),医療工学科の1限でした*2.
この日の記録↓
www.tnojima.net
やってみたら10年間でイロイロなことが起こった
ブログ更新したらSNSでお知らせするっていうのも10年間続けました.Twitter*3とか Facebook とか mixiとか Google+ とか.
講義で紹介した動画とかイラストとか,講義を準備するときに参考にした情報とか,興味のある者だけが確認しに行けばよい情報とか,他にもイロイロとオンライン情報があるので,そういうのをぜんぶブログにリンクさせておき,SNS→ブログ記事→関連情報,っていう移動を考えたからです.
そのために履修者にはSNS,特にTwitter利用を積極的にオススメして来たのですが,コレはみなさまの化学の理解を深めるためというよりは,違った方向に展開して行きました→ #北里つながろう プロジェクト
www.tnojima.net
あるとき化学の出版社 化学同人 @kagakudojin で編集のお仕事をされている方から連絡があり,ブログで公開しているような構成の,医療系学生向けの入門書を書いてみませんかっていうお誘いをいただきました.
コレが『はじめて学ぶ化学』となりました.出版以来増刷を重ね,2019年の第9刷が決定しています.
化学の講義には それなりに根性を入れて毎回の準備をしていて,その結果なのかどうかは別にして,2014年度に一般教育部が授業評価アンケートのランク付けをおこなったときに最優秀科目として表彰されました.
www.tnojima.net
教職員対象の事例紹介も依頼されたりしています.
www.tnojima.net
そういえば赴任初年度の2009年度から2016年度までは金曜2限の看護学部の化学も担当していたのですが,2012年度の看護学部の化学で,教室の隅っこで何か企てている人々がいて,何を相談してるんだろうなーって思っていたら,この人々は次の年にアイドル・コピー・ダンスのチームを結成しました→ 北里大学 winK♡ @winK_kitasato
この人々はすでに卒業していきましたが,winK♡ は学内外のファンを増やし現在も積極的に活動を続けております.私も学外ステージを観に行っております.
www.tnojima.net
化学の講義とは直接は関係ない大学関連FAQも公開してきました.もっともアクセスされている記事は「実験ノートには何を記録するのか?」です.
「実験ノート」でGoogle検索すると,Wikipediaや広告や大学制作サイトを除いた個人制作ページとしては5年以上にわたって上位一桁にランクインし続けています.
www.tnojima.net
このページを公開していた結果,マスコミから取材を受けたり,文科省検定中学理科教科書制作に協力することになったり,探求型学習に力を入れている高校とか,民間シンクタンクとか,都内の国立大学から講師を依頼されたりっていうことにつながりました.
www.tnojima.net
www.tnojima.net
www.tnojima.net
www.tnojima.net
www.tnojima.net
www.tnojima.net
こういうつながりから現在,さらに次のつながりに進歩しているものごともあります.
2冊目の書籍『誰にも聞けない実験ノートの書き方』も,この一連の流れの中から生まれたものです.
他にもイロイロあったのですが,化学の講義録を残そうって考えた時点では想像できなかった10年間になりました.
達成感は,ない
普段の私は ちょっと何かやると,それが台所の掃除とかイヌの風呂入れとかのレベルでも,「偉大な何かを成し遂げたかのような錯覚に包まれている!」などと叫んだりするのですが,
A4版にして1枚程度の仕事が終わり,偉大な何かを成し遂げたかのような錯覚を抱いているところ.
— 野島 高彦【化学】 (@TakahikoNojima) 2018年3月13日
10年続けたブログはすでに日常生活の一部になっており,特に何かあるわけでもありません.
そういえばこのブログを書き始めた次の年に読んだ本を思い出しました.

- 作者: いしたにまさき
- 出版社/メーカー: 技術評論社
- 発売日: 2010/11/27
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- 購入: 61人 クリック: 2,497回
- この商品を含むブログ (41件) を見る

- 作者: コグレマサト,いしたにまさき
- 出版社/メーカー: インプレス
- 発売日: 2012/08/23
- メディア: Kindle版
- クリック: 1回
- この商品を含むブログを見る
そういうものごとのほとんどには,さまざまな人々との出会いが関わっており,Webの世界をハイパーリンクする網目のように,これまでとは異なるレイヤーでのコミュニケーションが広がってきました.
良い意味で巻き込んだり巻き込まれたりっていうところです.
この先の世界
この先にどうなるのかはまったくわかりません.
ブログというメディアが今後も講義録を残して行くのに適切なのか,そもそもブログというものが残るのかどうかもわからないからです.
ブログという形を続けるかどうかは別として,公開できる形での講義記録は今後も続けて行きます.学生時代に履修した科目の記録が公開されていて,そこに自分とか,自分と同じ講義室で同じ時間を過ごした友人のコメントが残っているなんて,面白いだろうって思うからです.
そうそう,毎年,その年度最終回の事前配付物に書いていることがあります.
何年後かに,大学1年生だった頃の自分のコメントを探して読んでみるというのも悪くないだろう.もっとも,医療の専門家として大活躍,超多忙な毎日を送っている将来のあなたには,過去を振り返るヒマなんてないだろうけれどね.
書くのを止めちゃうと,コレができなくなるんだよね.