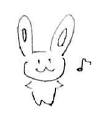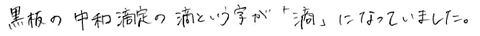キーワード
pKa,イオン積,塩,塩基,価数,緩衝作用,強塩基,強酸,酸,酸解離定数,弱塩基,弱酸,中和,中和滴定,電離度
講義内容要約
- H+を与えるのが酸で,受け取るのが塩基.
- 酸と塩基は相対的なもので,相手によって変わる.
- H+を1個与えられるのが1価の酸,2個与えられるのが2価の酸,3個与えられるのが3価の酸.
- H+を1個受け取れるのが1価の塩基,2個受け取れるのが2価の塩基,3個受け取れるのが3価の塩基.
- 水に溶かしたときにほぼ完全に電離する酸が強酸,一部が電離する酸が弱酸,ほぼ完全に電離する塩基が強塩基,一部が電離する塩基が弱塩基.
- 溶けている電解質の物質量のうち,電離している割合が電離度α.
- 酸が電離して生じたイオンのモル濃度の積を,電離していない物質のモル濃度の積で割ったのが酸解離定数Kaで,-log10KaがpKa.
- 水はわずかに電離していて,25 ℃においてはKw = [H+][OH-] = 1.0×10-14 mol2 L-2が成り立つ.これが水のイオン積.
- 酸と塩基とを過不足なく反応させる化学反応が中和反応で,中和反応で水といっしょに生じるのが塩(えん).
- 中和反応によって未知試料の酸あるいは塩基の濃度を測定する分析化学的手法が中和滴定.
該当する教科書のページ
第14章「酸および塩基とpH」の161ページから166ページあたりまで.

- 作者: 野島高彦
- 出版社/メーカー: 化学同人
- 発売日: 2012/04
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (53件) を見る
関連トピック
- 缶詰ミカンのつくりかた
- 缶みかんにするときのみかんの皮はどうやってむくのですか?/はごろもフーズ
- 吾妻川の河川中和事業
- 河川の中和/国土交通省関東地方整備局品木ダム水質管理所
確認テスト
出席者の声:みんなはこういうことを考えている/感じている/知りたいと思っている
字を創ってしまった.
●モル質量と物質量の違いが....しらべます.
●いまだにモル質量と物質量との違いがあいまい.
1モルあたりの重さがモル質量,何モルかが物質量.
●酸と塩基の話はおもしろかった.強酸,弱酸,強塩基,弱塩基の種類はどれくらい覚えればよいですか?
講義に出てくるのを覚えておけばOK. 数種類.
●酸性の川があることにまずおどろきました.また,みかん,いくら洗っていても,薬品を通したものを食べていいのか気になります(笑)
●みかんの皮を溶かす話,びっくりしました.●缶詰めのミカンが様々な薬品を使っているのを初めて知りました.
塩酸は胃袋の中にもあるからOK. 水酸化ナトリウムも仮に残っていても胃袋の中で中和されて食塩水になるからOK.ぜんぜん怖くない.
●黒板を半分にするやり方,見やすくて良かったです!
またやります.
●logが出てきて分からなくなりました.log苦手です.
●logの計算が難しそうだなと思いました.
●log難しく感じました(><)
コレ参照→高校数学のlogのあたりがアレな人々向けにpHって何なのか説明するよ
●しっかり復習したいと思います
●高校でやった記憶がうっすらありましたが,今日聞いて全然覚えていないことに気付きました.
●すごく理解できました.
●わかりやすかったです.
●ふくしゅうしてわかるようにします.
●計算問題は,やりこんでいこうと思いました.
●酸,塩基の強弱がいまだにわからなくなるときがあるので,暗記します!
●酸と塩基をみわけるのが苦手なので復習します.
●高校の時も苦手な分野だったのでがんばります.
●酸と塩基は好きな分野なのでテストでもがんばりたいです.
●この分野は好きだったので,より知識が深まりよかったです.
●最初は少し難しいかなと思っていましたが,やっているうちにだんだんわかってきました! 高校でも少しやった記憶があるので,より理解を深められるようにしっかりと復習をしていこうと思います.
●あと1時間やれば帰れる〜
●中和についてスッキリしました.話しっかりきいて理解してすすめたいです!
●フェノールフタレインがなつかしい!
●中和という響きがとてもなつかしかった.計算も手順を覚えれば理解できると実感した.
●酸解離定数,生化学の授業で,前期に教科書にのっていました.当時はただただKaという記号として見ていましたが,次にKaを見たときには,見方が変わると思います.
●公式だけでなくたくさん具体的な例を出してくれるのでイメージしやすく,分かりやすいです.
●教室くさいです・・・
出席者数推移
(1)44→(2)44→(3)43→(4)44→(5)43→(6)43→(7)42→
(8)43→(9)43→(10)41→(11)43→(12)43→(13)42→(14)41→
(16)41→(17)29→(18)35