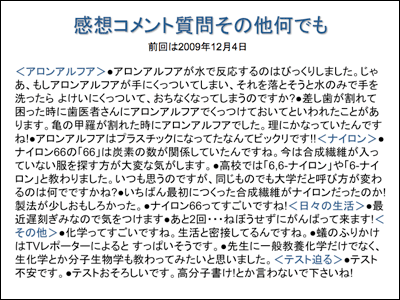前回の講義に対する感想コメントその他なんでも一括紹介
↑ここに書かれている内容に対してコメント&解説しました.
詳細は前回の講義録参照→第24回(2009-12-04)
(1)ペプチドの化学合成
今回は動画と説明図が多かったので板書をせずにすべてスライドで講義を進めました.ノートをとらずにスライドに集中できるよう,資料プリントを配布しておきました.
アミノ酸がアミド結合で複数個つながった分子がペプチドです.「短い」鎖長のものをオリゴペプチド,「長い」鎖長のものをポリペプチドと呼んでいますが,両者の間に明確な境目はありません.ポリペプチドのうち,機能と特異的立体構造をもったものがたんぱく質です.
ペプチドを記す際にはアミノ基を左側に,カルボキシル基を右側に置きます.それぞれN末端,C末端と呼びます.細胞内でペプチドはN末端から合成されますが,化学合成はC末端から進められます.
副反応が起こらないよう,脱水縮合に関係しない官能基を保護基で守っておくことがペプチド合成のポイントです.余計な反応が起こりそうな官能基を保護基で守っておいて,反応が終わったら保護基を外す,という操作の繰り返しになります.
この操作を全自動化したのがメリフィールドの固相合成法です.ビーズの表面にアミノ酸をくっつけておいて,ここに次から次へとアミノ酸を重合させて行く方法です.
(2)DNAの化学合成
ペプチド固相合成法と同じような方法で一本鎖DNAを化学合成できます.ここで合成されたDNAは以下に述べる(3)PCRや(4)DNA配列解読をはじめ,生命科学研究のあちらこちらで用いられます.
DNAについては、高校の生物で勉強したけど、化学目線で考えるのもおもしろいと思いました。
DNAは難しくてよくわかりません
参考図書

- 作者: JT生命誌研究館,工藤光子,中村桂子
- 出版社/メーカー: 講談社
- 発売日: 2007/12/21
- メディア: 新書
- 購入: 10人 クリック: 128回
- この商品を含むブログ (35件) を見る
(3)DNA増幅(PCR)
医療診断から犯罪捜査までいたるところでDNAの分析に用いられている操作がPCRです.条件が整っていれば髪の毛一本からでもDNAを分析可能な量まで増幅できます.
参考ムービー
PCR法についての説明が高校で教わったものよりもわかりやすくてよかったです。
欲しいDNAを増幅する時に95℃まで加熱し、変性させたDNAが温度を再度いい具合に調節するとプライマーがつくというのが画期的で不思議な気がします。DNAは熱に強いのでしょうか?
強いのです!
熱に対する強さという点では,たんぱく質はDNAにかないません.
PCRは遺伝子組換え実験でも用いられています.欲しい情報が記録された領域を増やして別のDNAにつなぐ操作で用いられているのです.バクテリアを用いた遺伝子組換え操作に関して,簡単に原理と操作手順の実際を紹介しました.
DNAの複製、大好きでした。大腸菌を使うのとかね、頭いい-!ってなってました。高校のとき。でもなんかそのへん勉強しすぎて今となってはもう飽きました。
ここで一休み.試験対策
来年1月15日に行われる期末試験に向けてチェックしておくべき項目を説明しました.
あーもうすぐテストなんですか.勉強しなきゃですね.嫌ですね.
試験・・・前期よりもいい点数とりたいです
試験対策、ありがとうございます。試験頑張ります!
テストこわくないです
(4)DNA配列解読
サンガー法を説明しました.4種類の蛍光色素標識ddNTPを用いるところがポイントです.
参考ムービー
色で読み取るとは・・・。そう考えた人は、本当に頭がいいなぁと思いました。
色つけるやつすんごー!! 感動! ちょっとまた楽しくなってきましたよ!
DNAの配列の解読の機械すごいです!
サンガー法の発明者であるサンガー博士は1918年うまれ.たんぱく質の配列決定法を開発して1回目のノーベル化学賞,DNAの塩基配列決定法を開発して2回目のノーベル化学賞を受賞しています.その他に博士はRNAの塩基配列決定法も開発しており,これも非常に重要な成果なので,もしかしたら3回目のノーベル化学賞受賞という可能性もあります.*1
今日は長生きしているおじい様がすばらしかったです。ノーベル賞を2つもとっているのにまだ取りたいというのは野心家でとてもいいと思いました。そういう貪欲な思いが研究には大切だと思いました。
その他のコメント
より良い医療を享受するため、より長生きするため・・・色々な理由で人は科学の発展を願うが、自然の法則に逆らっていないだろうか?読み解くのが難しい0.1%が箱の底に残る希望のような気がします。
「健康で長生きしたいと人間が願うこと」もまた自然の摂理の一部なのかもしれません.
ところでトマトなべが美味しくてしにそうです
テスト近いんですね、近いんですか? なんかその前にクリスマスケーキとかおせちとかおぞうにとか食べなきゃいけなくて忙しいので実感わきません。
しっかり食べてしっかり学びましょう.そして元気な看護師になりましょう.
来週で授業終了なんて早いですね。あっという間に感じます。
次回予告
医療や生命科学に関連する化学は今どこまで進展しており,これから先の10年間でどのように発展するのでしょうか.2019年の化学(医療関連)を考えます.2009年度の金曜2限化学講義は最終回になります.
来週の「2019年の化学を予想する」楽しみです。
次回最終だとおおおおおお早い!やだ!一週間で一番楽しかったのに!
やれやれ! おわっちゃうおわっちゃう
リンク
www.tnojima.netwww.tnojima.net

- 作者: MollyM. Bloomfield,伊藤俊洋,岡本義久,清野肇,伊藤佑子,北山憲三
- 出版社/メーカー: 丸善
- 発売日: 1995/03
- メディア: 単行本
- クリック: 2回
- この商品を含むブログ (143件) を見る

- 作者: MollyM. Bloomfield,伊藤俊洋,岡本義久,清野肇,伊藤佑子,北山憲三
- 出版社/メーカー: 丸善
- 発売日: 1995/03
- メディア: 単行本
- クリック: 2回
- この商品を含むブログ (75件) を見る
*1:と,私が大学生のときに生化学の講義でききました.それから約20年.もうこうなってくると何が何でも生き続けるしかないですね.